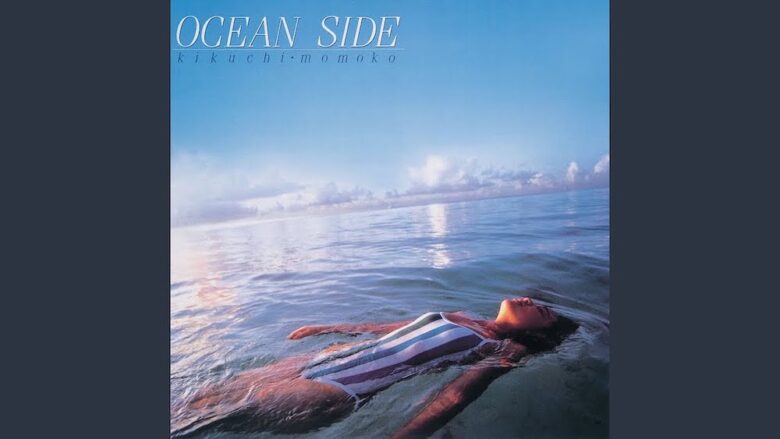2024年2月に4年ぶりの来日公演を開催するクイーン。これを祝して普段あまり語られる機会が少ないベース担当、現在は引退しているジョン・ディーコンが果たした功績を彼の提供曲を通じて検証します。
ジョンが持ち込んだ「サウンドの多様性」
まずは改めてクイーンのメンバー構成を。ボーカルのフレディ・マーキュリー、ギターのブライアン・メイ、ドラムのロジャー・テイラー、そしてベースのジョン・ディーコン。今回の主役、ジョンはクイーンの最年少メンバーであり(1951年8月19日生まれ)、バンドに最後に加入したメンバーです。
さらに言うと、ジョンはクイーンで唯一ソロアルバムを出していないメンバー。また、バンド中で唯一「歌わない」メンバーでもあります。物静かで表舞台に出るのも苦手な彼は、ロックスター然としたたたずまいの他の3人とは対照的な人物といえるでしょう。
ただし、そんなバンド内ではいまいち目立たないジョンこそが、クイーンの音楽性に多様な魅力をもたらしていた張本人だったのです。
クイーンのバンドとしての特徴は、4人のメンバー全員が曲を書くこと。メンバーそれぞれが大きなヒット曲を世に送り出している、優れたコンポーザーの集まりでした。これは他にあまり例を見ない、クイーンの最大の強みと言えます。
具体例を挙げていくと、「Bohemian Rhapsody」(1975年)はフレディ・マーキュリーがつくった曲、「We Will Rock You」(1977年)はブライアン・メイ、「Radio Ga Ga」(1984年)はロジャー・テイラー、といった具合。どれも伝記映画『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)でハイライト的に使われていたおなじみの名曲ですが、こうしたなかでジョンがどんなタイプの曲を書いていたかというと、いわゆる王道なクイーンの様式からはちょっと外れた曲でした。
ブラックミュージックとラテンミュージックの要素
ジョンがソングライティングを手がけた曲で最もよく知られているのが、1980年に全米1位になった「Another One Bites the Dust」。これはシックの1979年のヒット曲「Good Times」からインスピレーションを得たディスコソング。2021年に大ヒットしたBTS「Butter」のベースラインはこの2曲の系譜に属しています。
この「Anohter One Bites the Dust」に象徴されるように、ジョンがクイーンに持ち込んだ音楽的要素としてはまずブラックミュージック/ソウルミュージックがあります。
もうひとつ、ジョンはクイーンにラテンミュージックのエッセンスももたらしています。その代表的なヒット曲として真っ先に思い浮かぶのは、メンバーが女装したミュージックビデオが当時大きな話題になった1984年の「I Want to Break Free」(全英チャート最高3位)。リズムに注目して聴くとわかりやすいと思いますが、この曲はラテン音楽の影響が色濃く反映されています。
「80年代のクイーン」を導いたジョン
「Another One Bites the Dust」と「I Want to Break Free」。この2曲を挙げればクイーンにおけるジョンの存在の大きさ、ジョンがクイーンに寄与したものの大きさがよくわかると思います。特に「Another One Bites the Dust」はクイーンの歴史においても決定的な曲のひとつ。この曲がなかったら、80年代以降のクイーンのキャリアは微妙に違ったものになっていたはずです。
これはよく知られた話ですが、当初メンバーは「Another One Bites the Dust」のようなディスコソングをやることにあまり乗り気ではありませんでした。そんななか、当時フレディと親交を深めていたマイケル・ジャクソンから「絶対にリリースすべき!」との進言を受けてシングル化した結果、クイーンを代表する大ヒットになりました。ジョンのソングライティングの才能は、あのマイケルをも強く刺激したのです。
ここからはジョンがソングライティングを手がけた名曲を彼がクイーンに持ち込んだふたつの要素、ブラックミュージック編とラテンミュージック編に分けて3曲ずつ紹介します。
ブラックミュージック編
You’re My Best Friend (1975)
1975年のアルバム『A Night at the Opera』収録。ジョンが書いた曲がシングルに採用されたのはこの曲が初めて。イギリスのチャートで最高7位、アメリカでは最高16位にランクインするヒットになりました。タイトルから誤解しがちですが、これはジョンが妻ヴェロニカに向けて書いたラブソングです。
「You’re My Best Friend」の肝は、リズミカルでアタックが強いファンキーなエレクトリックピアノ。ここからは当時のスティーヴィー・ワンダーやビリー・プレストンの影響が聴き取れます。
クイーンのキーボードというとフレディが弾いている印象が強いかもしれませんが、ここではジョン自らが演奏。フレディは生のピアノに強いこだわりがあり、エレピは好きではないことから演奏を断ったそうです(ライブで「You’re My Best Friend」を披露する際はフレディがピアノを弾いていました)。
そもそも、この「You’re My Best Friend」自体メンバーがそんなに気に入っていなかった、という話もあるようです。実際、ライブでも1980年の『The Game』のツアーを最後にセットリストからは除外。このあたりは先述した「Another One Bites the Dust」のリリースをめぐるエピソードにも通じるものがあります。
これもまた、クイーンにおけるジョンの特異性がうかがえる話なのではないかと。やはりブラックミュージック色の強い曲は基本グループにそぐわないと見なされていたところがあったのかもしれません。
Cool Cat (1982)
1982年のアルバム『Hot Space』収録。これはジョンとフレディの共作。もともとデヴィッド・ボウイがバッキングボーカルを務めていましたが、本人的に不本意な仕上がりだったということでカットされた、という裏話があります。
「Cool Cat」は言わばクイーン流AOR、あるいはクイーン流のブラコンといったところでしょうか。フレディのスモーキー・ロビンソンばりの甘いファルセットボーカルも貴重ですが、なんといっても耳を引くのはクイーンにはめずらしい小気味良いギターカッティング。個人的にはアース・ウィンド&ファイアー「That’s The Way of the World」(1975年)を連想しました。
「ブライアン・メイがこんなファンキーなプレイを!」と思いきや、このギターを弾いているのは作者のジョン本人。「You’re My Best Friend」でフレディがエレピを弾くのを断ってジョンが演奏したのと同様に、やはりブラックミュージック色の強い「Cool Cat」のギターもソングライターであるジョンが自ら弾いているのは非常に興味深いものがあります。
この「Cool Cat」、最近ラッパーのJAY-Zが主宰するレーベル「Rock Nation」からデビューしたR&BシンガーのMaetaがカバーしていたことに象徴的ですが、クイーンにしてはかなり異質な曲。この路線で一枚アルバムをつくっていたらおもしろいことになっていたと思うのですが。
Pain Is So Close to Pleasure (1986)
1986年のアルバム『A Kind of Magic』収録。これも「Cool Cat」と同じくジョンとフレディの共作で、「Cool Cat」と同様フレディが全編でファルセットボーカルを披露する数少ない曲のひとつ。ジョン主導で作られた曲はクイーンにとって「特例」になりがちです。
この曲はベースラインの動きに注目して聴くとクイーン流のモータウンオマージュ(シュープリームスのオマージュ)であることがわかると思います。マドンナの「Like a Virgin」(1984年)などもそうですが、80年代にはモータウンサウンドをシンセポップとして焼き直したような曲が多く作られました。
この曲に関してもブライアン・メイが「自分たちにとってはかなりめずらしいタイプの曲」とコメントしていますが、そもそものリフのアイデアはブライアンが思いついたのだとか。ジョンは先の「Cool Cat」に続いてここでもリズムギターを担当しています。
ラテンミュージック編
Misfire (1974)
1974年のアルバム『Sheer Heart Attack』収録。ジョンがクイーンに提供した初めての曲として非常に歴史的価値の高い作品。カリブ音楽の影響をうかがわせる、小沢健二さんの「愛し愛されて生きるのさ」(1994年)にも似たさわやかで軽快なナンバー。ここでもすべてのギターをジョン自らが弾いています。
Who Needs You (1977)
1977年のアルバム『News of the World』収録。ジョンが単独で書いたカリプソ調のリラックスした曲。『News of the World』でジョンの曲といえばシングルにもなった「Spread Your Wings」が人気ですが、個人的に推したいのは断然こちら。ジョンはみずからアコースティックギターを演奏。マラカスはブライアン、カウベルはフレディが担当しています。
Rain Must Fall (1989)
1989年のアルバム『The Miracle』収録。ジョンとフレディの共作。これは当時のワールドミュージックブームに対するクイーン流(ジョン・ディーコン流)のリアクションとも受け取れるのでは。同時期のポール・サイモン、トーキング・ヘッズ、ピーター・ガブリエルあたりのアプローチを意識した痕跡もうかがえます。80年代後半のトレンドを偲ばせるドラムサウンドが印象的。
番外編:ジョンのポップセンスを堪能する2曲
You and I (1976)
1976年のアルバム『A Day at the Races』収録。ジョンが自らアコースティックギターを弾くロマンティックなラブソング。ピアノが牽引するポジティブな躍動感は、エルトン・ジョンやビリー・ジョエルが歌っても違和感がなさそう。個人的にはジョンが書いた曲の中でも上位にくるお気に入りですが、ライブでは一度も演奏されたことがないのだとか。当時フレディはインタビューで「ジョンの書く曲はアルバムを重ねるごとに良くなっている。実はちょっと心配になってきているんだ」と冗談交じりにコメントしています。
In Only Seven Days (1978)
1978年のアルバム『Jazz』収録。バケーション先での恋をロマンティックに歌い上げた甘美な曲。ここでもジョンはエレキとアコースティック、両方のギターを自ら演奏。曲調といい歌詞の題材といい、ジョンの独自性がよくわかる曲でしょう。
終わりに
以上、ジョン・ディーコンがソングライティングを手がけたクイーン作品から厳選した10曲を3つのセクションに分けて紹介しました。
もともと寡黙で控えめところがあったジョンは、映画『ボヘミアン・ラプソディ』も含めてフレディ・マーキューが亡くなったあとのクイーンの活動には基本的に参加していません。彼はフレディ不在のなかでクイーンとして曲をパフォーマンスすることにも強い抵抗があるようです。
そんなストイックさこそがジョンの大きな魅力であることは確かでしょう。ただ、もう表舞台に出てくることが望めそうもないからこそ機会あるごとにジョンの功績を確認する必要があるのではないかと考えています。